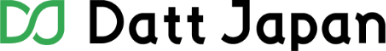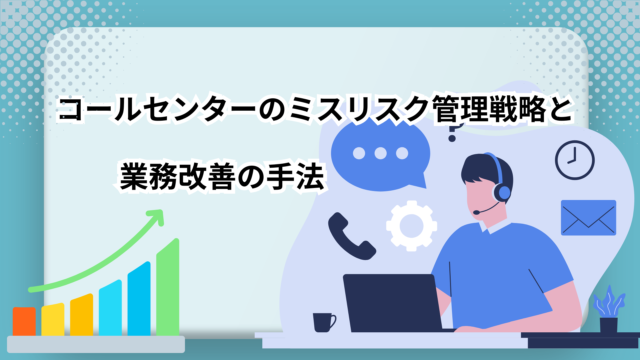社内業務の属人化や問い合わせ対応の負担に悩んでいませんか?「社内FAQシステム」を導入すれば、よくある質問を見える化し、対応の効率化・品質向上が実現できます。本記事では、社内FAQシステムの基本から作成・運用のステップ、効果的な改善方法までをわかりやすく解説します。業務効率化・コスト削減を目指す担当者必見の内容です。

社内FAQシステムとは?導入が求められる背景と役割

社内FAQシステムとは何か?定義と目的
社内FAQシステムとは、「社内で繰り返し発生する質問とその回答」を体系的にまとめ、社内の情報共有を円滑にするための仕組みです。FAQは「Frequently Asked Questions」の略で、「よくある質問」を意味します。特に人事・総務・情報システムなど、各部署への問い合わせが集中しやすい業務領域では、社内FAQシステムを整備することで業務負担を大きく軽減できます。
社内FAQシステムの主な目的は次のとおりです。
- 社員が自分で情報を探しやすくすることで、自己解決を促進すること
- 繰り返し発生する問い合わせ対応を削減し、業務効率を向上すること
- ノウハウやナレッジを文書化し、属人化を防ぐこと
これにより、組織全体の生産性向上と、情報の透明性が同時に実現されます。
FAQとQ&Aの違い
FAQと混同されがちな用語に「Q&A」があります。両者は似ていますが、明確な違いがあります。
|
用語 |
特徴 |
用途 |
|
FAQ |
頻出質問に対し、網羅的に体系化された回答集 |
社内全体・マニュアル的に活用 |
|
Q&A |
単発の質問と回答のセット |
個別対応・チャット等の履歴ベース |
社内FAQシステムは、あくまで共通化・標準化された「社内ナレッジの集約」を目的としており、属人的なQ&Aのやり取りとは性質が異なります。
社内FAQシステムが注目される理由
近年、社内FAQシステムが注目される背景には、以下のような社会的・組織的な要因があります。
- 人手不足の深刻化:問い合わせ対応のための人材確保が難しくなっている
- テレワークの拡大:離れた場所でも自己解決できる仕組みが必要である
- 業務の複雑化・情報の氾濫:従業員が必要な情報にすぐアクセスできない
- DX推進による業務効率化ニーズ:問い合わせ対応業務のデジタル化・自動化
とくにDX文脈では、「社内FAQシステム+チャットボット」や「ナレッジシステム」といったツール連携で、さらなる省力化・高速化が求められています。
社内FAQシステムの導入メリット

社内FAQシステムを導入することによって、単に「よくある質問をまとめる」だけでなく、組織全体の生産性や業務効率を大幅に向上させることができます。ここでは代表的なメリットを、視認性の高い表とともにご紹介します。
問い合わせ対応の時間削減
社内FAQシステムの最大の効果は、各部署への問い合わせ件数の削減です。たとえば「勤怠申請の方法」「メール設定」「PCの初期設定」など、繰り返される基本的な質問に対して、事前に回答を用意しておくことで、担当者が同じ説明を何度も行う必要がなくなります。これにより、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
ナレッジ共有による業務の標準化
社内FAQシステムには、業務の進め方や判断基準が集約されるため、組織内のナレッジを「誰でもアクセスできる形」で共有できます。これは属人化の解消や、対応品質の平準化にもつながります。
特に対応のばらつきが許されない業務(ITサポート・人事制度など)では、標準化が業務リスクの低減にも寄与します。
新人教育・研修コストの低減
新入社員や異動者が業務に慣れるまでには、多くの「質問」と「確認」が発生します。社内FAQシステムがあれば、彼らが自ら情報にアクセスし、疑問を解決できる環境を提供できます。
その結果、OJT担当者の負担軽減にもつながり、教育コストを抑えながら即戦力化を促進します。
社内FAQシステム導入によるメリット・効果
|
メリット・効果 |
効果が見込める部門 |
|
|
問い合わせ対応の時間削減 |
定型的な質問に対応不要となり、業務効率が向上 |
総務・情シス・人事 |
|
ナレッジの標準化・共有 |
対応品質のばらつきを防ぎ、誰でも同じ情報にアクセス可能に |
サポート部門・管理部門 |
|
教育コストの削減 |
新人や異動者が自力で業務を習得しやすくなる |
全社(OJT対象者が多い部門) |
|
業務リスクの軽減 |
間違った対応・属人化によるトラブルを予防 |
法務・労務・規定関連部門 |
このように、社内FAQシステムは単なる情報整理ツールではなく、業務負荷の削減・教育強化・ナレッジ定着を同時に実現する「業務改善施策」として、あらゆる企業に活用されています。

社内FAQシステムの作り方|基本の5ステップ

社内FAQシステムの構築は、一度で完璧なものを作る必要はありません。むしろ、「小規模から始めて改善、拡大を重ねる」ことが成功の秘訣です。ここでは、初めて社内FAQシステムを導入する企業でも実践しやすい基本ステップを紹介します。
ステップ① よくある質問の収集
まず最初に行うべきは、「どんな質問が多いのか?」を洗い出すことです。以下のような社内情報源を活用すると、網羅的に収集できます。
- 社内チャットツール(Slack・Teamsなど)の過去ログ
- メールでの問い合わせ内容
- ヘルプデスクや人事への口頭質問
- 過去の研修・OJT時の質問内容
ポイントは、「実際に社員が困っていること」をベースにすることです。仮説ではなく実データに基づくFAQ構成が重要です。
ステップ② 回答の作成とルール化
質問を集めたら、それぞれに対する回答を作成します。このとき重要なのは、「誰が読んでもわかる明確な表現」で書くことです。
- 専門用語はできるだけ避ける(または補足説明をつける)
- 一文は短く簡潔に
- スクリーンショットやリンクを活用して視覚的に補足
また、チームで分担してFAQを作成する場合は、「記載ルール」を事前に定めておくと、文体や表現が統一されます。
ステップ③ カテゴリ・検索性の設計
FAQは、情報の探しやすさ=「検索性」が命です。カテゴリー分類やタグ付け、見出しの整理などに工夫が必要です。
- 大カテゴリ(例:人事・IT・勤怠・福利厚生など)で分類
- 質問のタイトルは、検索キーワードを意識した自然な表現にする
- ナンバリングや階層構造を取り入れる
答えを見つけづらいFAQは「使われない」原因になるため、このステップは軽視できません。
ステップ④ FAQの公開と周知
作成した社内FAQシステムは、社員が日常的にアクセスできる場所に配置し、しっかり周知することが不可欠です。
- 社内ポータルサイトやイントラネットへの掲載
- チャットツールの固定リンク・ピン留め機能の活用
- 全社メールや定例ミーティングでの告知
FAQを「あることは知っているが、どこにあるかわからない」という状況を避けましょう。
ステップ⑤ 定期的な更新と改善
一度作成した社内FAQシステムも、時間とともに陳腐化します。制度改定、システム変更、新人からの新しい質問などに応じて、定期的な見直しが必要です。
- アクセス数や検索ワードを分析し、閲覧されていない項目を改善
- チャットやアンケートからの「未掲載質問」を反映
- 定期的なレビュー日を設け、担当者がチェック
「作って終わり」ではなく、運用と改善の継続が社内FAQシステムの価値を高めます。
社内FAQシステムの運用で注意すべきポイント

社内FAQシステムは、導入しただけでは十分に機能しません。定着させ、活用され続けるためには、日々の運用の工夫が欠かせません。この章では、社内FAQシステムが「使われない」原因と、その対策について解説します。
FAQが「使われない」原因と対策
せっかく整備したFAQも、実際に活用されないケースは少なくありません。よくある原因とその解決策は以下のとおりです。
|
よくある課題 |
原因例 |
対策案 |
|
社員がFAQの存在を知らない |
周知不足、掲載場所がわかりにくい |
公開時に全社告知、ポータルやチャットに常設リンクを設置 |
|
FAQの中身が古い・使えない |
更新されていない、回答がわかりにくい |
定期的な見直し、アクセス数の分析による改善 |
|
検索しても情報が見つからない |
キーワード設計が不十分、分類があいまい |
質問タイトルに自然な検索語句を含める、カテゴリの再整理 |
FAQが「使われない」=運用の仕組みが整っていないサインです。定期的に現場の声を拾い、改善を積み重ねることが重要です。
運用ルールの整備と責任者の明確化
FAQを形骸化させないためには、「誰が、どのように、いつ更新するか」という運用ルールの明文化が欠かせません。
- 管理者(担当者)を部署ごとに明確にしておく
- 更新フローを決めておく(例:半年に一度、必ずレビュー)
- 社内システムと連携する場合、権限やログ取得の仕組みも検討
特にFAQの内容に責任が伴うような項目(労務・経費・ITなど)については、内容の正確性と更新責任の所在をはっきりさせておく必要があります。
検索性・導線の工夫が浸透を左右する
いかに内容が良くても、「探しにくい」「見つからない」FAQでは意味がありません。社内FAQシステムの利用率を高めるには、次のような導線設計の工夫が有効です。
- 社内チャットツールとの連携(BotからFAQリンクを返すなど)
- ポータルサイト上の目立つ位置への配置
- 検索バーの設置と予測変換キーワードのチューニング
- アクセスログ分析を通じた改善(検索されているがヒットしない単語など)
FAQの「見つけやすさ」は、導入効果を大きく左右する要素です。運用設計の段階から、社員の行動動線に自然に組み込むことを意識しましょう。
まとめ|社内FAQシステムの活用は小さく始めて改善を回そう
社内FAQシステムは、社員のよくある質問を可視化・共有することで、業務の効率化・属人化の解消・教育コストの削減といった多くの効果を発揮します。しかし、その真価を発揮するには「作って終わり」ではなく、継続的な運用と改善が欠かせません。
社内FAQシステムは属人化・非効率業務の打開策
どの会社にも「この人に聞けば分かる」「あの部署でしか把握していない情報」が存在しがちです。これが属人化の温床となり、問い合わせの集中や業務停滞を招く原因になります。社内FAQシステムは、そのような情報を共有化・体系化し、全社員が同じ情報にアクセスできる仕組みをつくります。
作って終わりにしない、改善が成功の鍵
FAQは一度作れば永続的に機能するわけではありません。制度改定、業務フローの変化、IT環境のアップデートなど、企業の情報は日々更新されます。だからこそ、定期的な見直しと社内フィードバックの活用が、社内FAQシステムの定着と成果につながるのです。
ツール選びや設計に迷ったら専門家への相談も視野に
「FAQを作っても使われなかったらどうしよう…」
「何から始めればよいか分からない」
「システム連携や更新ルールの設計が難しい」
そんなお悩みをお持ちのご担当者様は、外部のノウハウを活用することも有効な選択肢です。ダットジャパン株式会社では、FAQの設計支援からチャットボット連携・更新ルールの設計まで、運用定着まで見据えた社内FAQシステム構築サポートを提供しています。
短納期・低コストでの導入をご希望の企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。
▶【社内FAQシステム構築・運用】に関するお問い合わせはこちら
次世代の業務効率化は、「よくある質問」の整理から始まります。
まずは小さな社内FAQシステムから、一緒に業務改善をスタートしませんか?