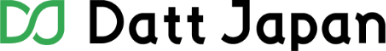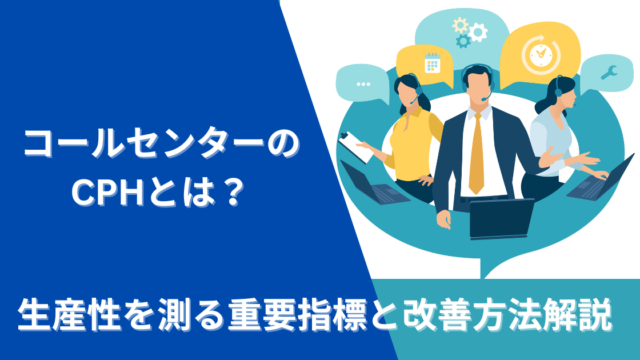企業が成長を続けるためには、顧客対応の質の向上と業務効率の両立が求められます。しかし、自社だけで対応を行うと人手不足やコストの増加が課題となりやすく、対応の品質を維持することが難しくなる場面もあります。そこで注目されているのが、カスタマーサポート業務の外部委託です。委託には、コスト削減・対応品質向上・人材確保の柔軟性など多くのメリットがありますが、一方で情報共有やノウハウ蓄積の難しさといったデメリットも存在します。この記事では、委託の仕組みや注意点、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

カスタマーサポート委託とは?基本的な仕組みと背景
カスタマーサポートの委託とは、自社の顧客対応業務を外部の専門業者に任せる仕組みのことを指します。電話やメール、チャットによる問い合わせ対応など、日常的な顧客との接点業務を外部の委託会社が担うことで、コスト削減や業務効率化、対応品質の向上といった効果が期待できます。特に近年では、業務の複雑化や人手不足の深刻化により、自社内ですべてを処理するのが困難になってきた企業を中心に、委託ニーズが高まっています。
また、カスタマーサポートは企業イメージを左右する重要な業務であるため、専任体制を構築しづらい中小企業やベンチャー企業では、品質を落とさずに安定した対応を実現する手段として委託が選ばれるケースが増えています。
なぜ今、外部委託が注目されているのか
カスタマーサポートの外部委託が注目される背景には、以下のような社会的・業務的な変化があります。
- 人材不足による内製対応の限界 :自社で対応要員を確保することが難しくなり、業務負担の分散が求められているためです。
- 顧客対応チャネルの多様化 :電話だけでなく、メール・チャット・SNSなど、対応手段が増えたことで運用が複雑化しています。
- 顧客満足度の重要性が増している :対応の質がブランドイメージやリピート率に直結するようになったため、プロによる対応が求められる傾向にあります。
- コスト削減への意識 :オペレーションコストを削減しつつ、高品質なサービスを維持する方法として注目されています。
これらの背景から、限られた人材・予算でも効率的に業務を回せる方法として、外部委託が現実的な選択肢として導入され始めています。
委託と代行・アウトソーシングの違い
「委託」「代行」「アウトソーシング」という言葉は似たように使われがちですが、その意味や契約内容には明確な違いがあります。
- 委託(業務委託): 業務の一部または全部を外部企業に任せる契約形態。業務内容の指揮命令権は委託元にあるのが特徴です。
- 代行 :特定の業務を他者に任せてその業務を代わりに遂行してもらう行為を指し、やや曖昧な使われ方をすることもあります。広告代理や事務代行などが代表例です。
- アウトソーシング :広義の委託全般を指す言葉で、社外の専門業者に業務プロセスを任せることを意味します。ITや人事、カスタマーサポートなど、分野を問わず広く使われます。
カスタマーサポートの外部化では、業務委託契約として委託する形が一般的です。自社の課題や求めるサポート範囲に応じて、最適な委託形態を選ぶことが求められます。
カスタマーサポートを委託するメリット
カスタマーサポート業務を外部に委託することで、自社ではカバーしきれない部分を専門のプロに任せることができるという大きなメリットがあります。業務品質の向上に加え、コストの最適化や対応体制の強化といった、企業の課題解決に直結する効果が期待できます。
顧客対応の品質向上とプロによる対応
カスタマーサポートを専門に行う委託先では、教育されたオペレーターが顧客対応にあたるため、対応品質が安定しやすくなります。表現や言葉遣い、クレーム対応のスキルなど、経験に基づいた応対が期待でき、企業ブランドの信頼感向上にもつながります。
- 顧客満足度を意識した丁寧で一貫性のある対応
- 業務フローやFAQに基づく迅速な問題解決
- 専門知識や業界知識を持った人材の活用
自社で新たにノウハウを構築するコストや時間を削減しつつ、初日から高い水準のサービス提供が可能となります。
より専門的なテクニカルサポート委託に関する選び方や注意点については「【顧客満足度UP】テクニカルサポート委託のメリット・デメリットと選び方のポイントを徹底解説」で詳しく解説しています。
コスト削減と社内業務の効率化
カスタマーサポートの内製化には、人件費・教育コスト・管理工数など多くのリソースが必要です。委託することで、これらのコストを削減しつつ、業務の効率化を図ることができます。
- 採用や研修にかかる人的コストの削減
- 機器・システムなどインフラ投資の最小化
- 社内人員を本来の中核業務に集中させる
また、業務量に応じた契約ができる可変型の料金プランを採用すれば、閑散期・繁忙期に合わせた柔軟なリソース調整も可能になります。
カスタマーサポート委託の費用相場や料金体系については「カスタマーサポートの料金体系と費用相場を解説!費用対効果や外注費を抑えるコツも!」で詳しく解説しています。
24時間対応や多言語サポートなどの拡張性
自社内では難しい24時間365日の対応や多言語対応も、外部委託なら対応可能な場合が多くあります。グローバル展開を視野に入れている企業や、深夜・早朝にも問い合わせがある業種では、顧客対応の幅を広げる強力な手段になります。
- 24時間体制による緊急時対応や深夜対応が可能
- 英語・中国語などの多言語対応で海外ユーザーにも対応
- チャット・メール・電話など複数チャネル対応の強化
このような対応体制の拡張性によって、企業は顧客基盤を広げることができ、機会損失を最小限に抑えることができます。
カスタマーサポートを委託するデメリットとリスク
カスタマーサポート業務の委託には多くのメリットがある一方で、自社で対応しないことによるリスクや課題も存在します。特に長期的な運用やブランドイメージの観点からは、慎重な判断が求められます。ここでは、委託によって生じる代表的なデメリットとそのリスクについて解説します。
自社ノウハウが蓄積しにくい課題
カスタマーサポートを外部に任せると、顧客対応に関するデータや知見が自社に蓄積されにくくなります。対応ログや顧客の声はマーケティングや商品改善に役立つ重要な情報源ですが、外部委託ではそのフィードバックを活用する体制が不十分になりがちです。
- 顧客対応で得られる生の声が社内に届きにくい
- 問題の傾向分析や改善提案が他部門に伝わりづらい
- 顧客との接点を持つ部門が戦略的に活用されない
委託先との情報連携の仕組みを整備しないと、自社の成長機会を逃すリスクがあるため、運用設計の段階から意識する必要があります。
情報共有やセキュリティの難しさ
外部企業と連携する以上、情報漏洩リスクや社内システムとの連携におけるセキュリティ対策が不可欠です。特に個人情報や顧客データを扱うサポート業務では、わずかな管理ミスが大きなトラブルにつながる可能性があります。
- 社内外でのデータの取り扱いルールが統一されていない
- 委託先のセキュリティポリシーが不明確
- 担当者変更や引き継ぎ時に情報伝達が滞るリスク
委託前にセキュリティ基準や業務範囲、アクセス権限を明確にし、情報共有のルールを文書化しておくことが不可欠です。
委託先による対応品質のばらつき
カスタマーサポートは「対応者の質」に大きく左右されます。外部の委託先は自社と異なる文化・評価制度でスタッフを管理しているため、オペレーターごとの品質のばらつきが生じる可能性があります。
- 対応の言葉遣いや態度に差がある
- 商品知識やサービス理解に個人差が出やすい
- 一部の対応がブランドイメージを損なうリスク
特に長期契約や複数拠点での運営を行う場合、マニュアル整備やモニタリング体制が重要な鍵となります。品質を一定に保つためには、継続的なトレーニングとフィードバックの仕組みを整える必要があるでしょう。

委託先を選ぶ際のポイントと確認事項
カスタマーサポートを外部に委託する際は、委託先の選定が成功の鍵を握ります。単に費用や知名度で決めるのではなく、業務の質・セキュリティ・対応体制など多角的に比較検討することが重要です。ここでは、委託先を選ぶうえで特に注意すべき項目を解説します。
実績・業務範囲・対応体制の確認
委託先を選定する際は、業界での実績や、対応可能な業務範囲をしっかりと確認しましょう。自社の業種やサービスに対応できるかどうかがポイントとなります。
- 過去の導入実績(業界・業種)
- 対応可能なチャネル(電話・メール・チャットなど)
- 営業時間や対応可能な曜日・時間帯
- 急な増員や繁忙期への柔軟な対応体制
また、マニュアルの整備状況や教育体制、担当者の質や人数など、実際に業務を遂行するオペレーターのレベルにも目を向ける必要があります。
セキュリティ・情報管理体制の評価
カスタマーサポート業務では、顧客の個人情報や取引内容を取り扱うケースが非常に多く、セキュリティ対策は欠かせません。委託先がどのような情報管理体制を整備しているか、事前に詳細まで確認する必要があります。
- 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の有無
- PマークやISMSなどの認証取得状況
- 顧客データの取り扱い・保管方法
- 社員・スタッフへの情報セキュリティ教育の実施状況
- 万が一のインシデント発生時の対応フロー
これらを事前にヒアリング・確認し、自社の情報セキュリティ基準に合致しているかどうかを判断することが重要です。
コスト・料金体系の比較と注意点
委託コストは外注検討時に最も気になるポイントの一つです。ただし、料金が安い=良い委託先とは限りません。料金体系の内訳や課金方式を理解し、費用対効果で判断する視点が必要です。
- 月額固定制か従量課金制か(またはハイブリッド型か)
- 初期費用・運用費・マニュアル作成費用などの追加費用の有無
- サービスレベル(対応件数・時間帯・多言語対応など)とのバランス
- サービス終了時のデータ返却や契約解除条件
見積もり段階で料金に含まれる内容を明確にし、想定外のコストが発生しないよう契約前に丁寧に確認することが大切です
委託活用の成功事例と運用改善のコツ
カスタマーサポートの委託は、単なる業務の外注ではなく、顧客満足度や業務効率を大きく向上させる手段です。ここでは、委託を活用して成果を上げた実際のケースと、スムーズな運用のための工夫を紹介します。
委託導入で改善された具体的事例紹介
カスタマーサポートを委託することで、応対品質や対応スピードが向上し、クレーム件数が大幅に減少したという事例は多く存在します。以下は代表的な改善例です。
- ECサイト運営会社の事例
社内で対応していたメール・電話対応を委託。プロのオペレーターによる対応で顧客満足度が向上し、レビュー評価も安定。社内リソースはマーケティングや商品開発へと集中できた。 - ITサービス企業の事例
サポート窓口の一部を多言語対応が可能な委託先に外注。海外ユーザーへの対応力が向上し、グローバル展開をスムーズに進められた。 - 人材サービス会社の事例
求人応募者からの問い合わせを外部委託。繁忙期の問い合わせ対応が安定し、離脱率が減少。コストは従来比で約25%削減という結果に。
このように、委託の活用は業務改善・コスト削減・顧客満足向上のすべてに貢献する可能性があります。
自社と委託先で連携を取る工夫と仕組み
委託を成功させるには、自社と委託先が密に連携し、同じ目標を共有することが不可欠です。運用改善を進めるために、以下のポイントが重要です。
- マニュアルの整備と定期的な見直し
業務フローやFAQを委託先と共有し、定期的に内容を更新することで対応の標準化と品質維持を図ります。 - 担当者間の定期ミーティングの実施
運用課題や問い合わせ内容の傾向を共有する機会を設け、改善提案を委託先からも積極的に受ける体制を構築します。 - 業務進捗・KPIの可視化と共有
応答率、一次解決率、CS(顧客満足度)などを定期的にレポート化し、双方で成果を確認しながらPDCAを回すことが重要です。 - セキュリティや個人情報管理のルールを統一
自社と委託先で異なる基準にならないよう、事前にセキュリティポリシーや対応ルールを明文化しておくことがリスク軽減につながります。
これらの連携ポイントを抑えることで、単なる業務委託ではなく、ビジネスパートナーとしての関係構築が可能となります。
まとめ
カスタマーサポートの委託は、業務効率化と顧客満足度向上を同時に実現できる有効な手段です。プロによる対応で品質の安定や多言語・24時間体制の実現も可能となり、自社のリソースを中核業務に集中させることができます。一方、情報共有や対応品質のバラつきなど、委託にはリスクもあります。そのため、信頼できる委託先を選び、明確な目的とルールで連携することが重要です。委託を戦略的な顧客対応の進化と位置づけ、自社の課題や目標に応じた体制を構築することが、これからの顧客対応の鍵となります。
低コスト!高品質!運営実績25年のダットジャパンコールセンターのご案内
ダットジャパンコールセンターは、お客様の課題解決とビジネス成長を、実践的なコンタクトセンターソリューションで全力サポートします。
- コスト削減 & 業務効率化: 経験豊富な専門家が最新技術とノウハウで実現。
- 迅速導入 & 柔軟対応: 最短3ヶ月での立ち上げ/移行、ニーズに合わせた柔軟な対応力。
- 幅広いサービス & 大手実績: コールセンターからデジタル支援、BPO、コンサルまで。大手企業での導入実績多数。
- 最新技術 & 多言語対応: AI・CRM等の最新技術活用、日英対応でグローバル展開も支援。
理想の顧客体験を実現し、ビジネスの可能性を広げませんか?まずはお気軽にご相談ください。詳細は公式サイト (https://datt-contactcenter.jp/) をご閲覧下さい。