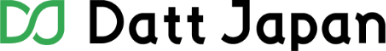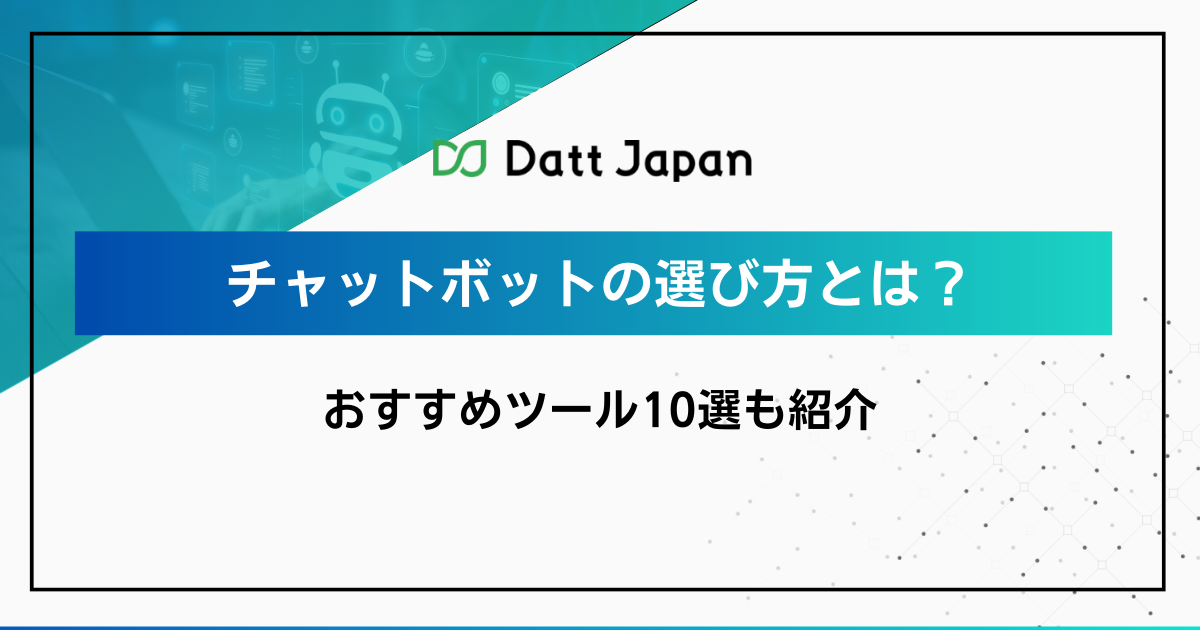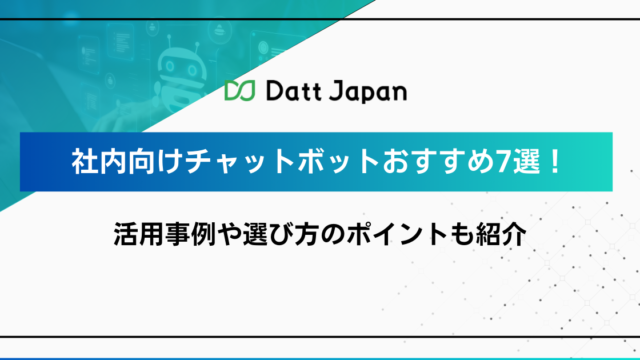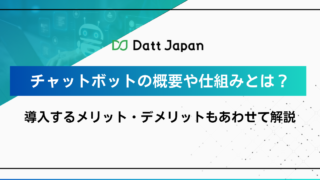近年、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進において、チャットボットの導入が重要な施策として注目を集めています。
24時間365日稼働可能で人件費の削減に貢献するだけでなく、顧客満足度の向上やビジネスプロセスの効率化にも大きく貢献しています。
しかし、技術の進歩に伴い、チャットボットの種類や機能は多様化しており、自社に最適なものを選ぶのが困難になってきています。
本記事では、チャットボットの基礎知識から選び方のポイント、さらにはおすすめツール10選などをご紹介します。

チャットボットの選び方
チャットボットを導入する際には、まず自社のニーズや目的を明確にし、それに合った種類や機能を持つものの選択が重要です。
単なるコスト削減や業務効率化だけでなく、顧客体験の向上や従業員の働き方改革など、多角的な視点での検討が必要です。
また、導入後の運用体制や改善計画についても事前に考慮しておけば、より効果的な活用が可能になります。
種類
チャットボットは大きく分けて
・AI型
・シナリオ型
の2種類があります。
それぞれに特徴があり、用途や予算に応じて選択する必要があります。近年では、これらを組み合わせたハイブリッド型も登場しており、選択肢はさらに広がっています。
AI型
AI型チャットボットは、人工知能技術を活用して顧客との対話を行います。入力された質問や顧客情報をもとにAIが分析し、適切な回答を返すシステムです。
たとえば、「返品の方法を教えてください」という質問に対して、商品の種類や購入時期などの情報を総合的に判断し、最適な返品方法を案内できます。
AI型チャットボットは、さらに、、、
・機械学習型
・独自AI型
・RAG型
などに細分化されています。
機械学習型
対話データを蓄積しながら徐々に精度を向上させていくタイプで、長期的な運用での効果が期待できます。
独自AI型
特定の業界や業務に特化した独自の人工知能を搭載しており、専門的な対応が可能です。
RAG型
既存の文書やFAQをもとに回答を生成する能力に優れており、導入後すぐに高精度な応答が可能という特徴があります。
シナリオ型
シナリオ型チャットボットは、予め設定したシナリオ(ルール)に従って会話を進めていくタイプです。
たとえば、飲食店の予約受付を行うチャットボットの場合、「来店日時」「人数」「コース選択」といった項目を順番に確認していき、最終的に予約を確定するというフローを作成できます。
シナリオを準備する手間は必要ですが、AI型に比べて導入コストが抑えられる傾向にあります。また、想定される質問に対して正確な回答を返せるため、金融機関での口座開設手続きや、医療機関での診察予約など、正確性が求められる業務に適しています。
最近では、シナリオ型の特徴を活かしながら、簡単なAI機能を組み合わせたハイブリッド型も登場しています。これにより、定型的な業務はシナリオで対応しながら、想定外の質問にもある程度対応できる柔軟性を実現しています。
仕組み
チャットボットの会話の仕組みは、主に
・選択肢型
・辞書型
・選択肢+辞書型
・ログ型
の4つに分類されます。
それぞれの特徴を理解することで、自社の要件に合った仕組みを選択できます。
選択肢型
選択肢型は、チャットボットが選択肢を提示し、ユーザーがその中から該当する項目を選択する形式です。
たとえば、ECサイトのチャットボットで「どのようなご用件ですか?」という質問に対して、「商品について」「配送について」「返品について」といった選択肢を表示し、ユーザーの選択に応じて次の質問や回答を提示していきます。
この方式は、ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けるというメリットがあります。
特に、スマートフォンでの利用を想定する場合、テキスト入力の手間を省けるため、ユーザビリティが高いと言えます。
一方で、提示された選択肢以外の質問には対応できないという制限があります。
辞書型
辞書型は、主にAI型チャットボットに搭載されている仕組みで、ユーザーの質問に含まれるキーワードを認識し、適切な回答を返す形式です。
たとえば、「返品の期限はいつまでですか?」という質問から「返品」「期限」というキーワードを抽出し、関連する回答を提供します。
この方式は、自然な会話が可能で、ユーザーの多様な表現にも対応できるというのが利点です。
ただし、的確な回答を返すためには十分なデータの蓄積が必要で、導入初期は精度が低い場合があります。また、同音異義語や文脈理解が必要な質問への対応には課題が残ります。
選択肢型+辞書型
選択肢型と辞書型を組み合わせた方式です。
基本的な案内は選択肢で行いながら、詳細な質問はテキスト入力で受け付けられます。たとえば、商品カテゴリーは選択肢から選んでもらい、具体的な商品の特徴については自由に質問できるといった使い方が可能です。
この方式は、ユーザビリティと柔軟性のバランスが取れており、多くの企業で採用されています。特に、FAQシステムと組み合わせることで、効率的な情報提供が可能になります。
ログ型
ログ型は、過去の対話データを蓄積し、それをもとにAIが回答を生成するタイプです。
たとえば、カスタマーサポートでよくある質問とその回答パターンを学習し、より自然な対話を実現します。
時間とともに精度が向上していく特徴があり、長期的な運用を前提とした場合に効果を発揮します。
機能
チャットボットには、用途に応じてさまざまな機能が搭載されています。
主な機能として
・FAQ型
・処理代行型
・配信型
があります。
FAQ型
FAQ型は、よくある質問と回答をチャットボット形式で提供する機能です。
従来のFAQページとは異なり、対話形式で情報を提供することで、ユーザーは必要な情報により早くたどり着けます。
たとえば、「商品の保証について知りたい」という質問に対して、製品カテゴリーや購入時期などを確認しながら、該当する保証内容を案内できます。
また、質問の傾向を分析することで、FAQコンテンツの改善にも活用できます。
よく質問される内容や、回答に至らなかった質問を把握すれば、情報提供の質を継続的に向上させることが可能です。
処理代行型
処理代行型は、ユーザーが入力した情報をもとにシステム処理を実行する機能を持つタイプです。
たとえば、ホテルの予約システムと連携したチャットボットでは、宿泊日や部屋タイプの希望を確認し、空室状況の確認から予約確定までをワンストップで行えます。
カレンダーアプリとの連携も可能で、営業担当者のアポイント調整や、社内の会議室予約などにも活用可能です。最近では、RPAと組み合わせることで、より複雑な業務の自動化も実現しています。
配信型
配信型は、プッシュ通知的な機能を持つチャットボットです。
たとえば、ECサイトと連携して商品の配送状況を通知したり、キャンペーン情報を配信したりできます。
特にLINEなどのメッセージングプラットフォームと連携すれば、高い開封率とエンゲージメントを実現できるでしょう。また、ユーザーの行動履歴や属性に基づいてパーソナライズされた情報の配信も可能です。
たとえば、過去の購買履歴をもとにおすすめ商品を提案したり、誕生日や記念日に合わせて特別なクーポンを配信したりすれば、顧客満足度の向上につながるでしょう。
サービス
チャットボットを提供している企業によって、サービス形態は大きく異なります。
・セルフ型
・クラウド型
・オンプレミス型
それぞれの特徴を理解し、自社の体制や予算に合わせて最適な形態の選択が重要です。
セルフ型
セルフ型は、初期設定から実装まですべて自社で行うタイプのサービスです。
導入コストを抑えられる反面、チャットボットに関する専門知識が必要となるため、導入までのハードルが高い傾向にあります。
特に、シナリオの作成やAIの学習データの準備など、専門的なスキルが求められる部分が多く存在します。
ただし、自社でカスタマイズできる範囲が広いため、独自の要件に柔軟に対応できるのがメリットです。
また、運用を通じて社内にナレッジが蓄積されるため、長期的な展開を考えている企業にとっては魅力的な選択肢となります。
クラウド型
クラウド型は、初期設定などをベンダーがサポートしてくれるタイプです。
ベンダーのサーバーにシステムが設置されるため、高機能かつスピーディーな導入が可能です。また、セキュリティ対策やバックアップなどの運用面もベンダーが担当するため、システム管理の負担を軽減できます。
さらに、他社の導入事例やベストプラクティスを活用できることも大きな利点です。たとえば、同業他社での成功事例をもとにシナリオを作成したり、効果的な運用方法についてアドバイスを得たりできます。
また、定期的なバージョンアップにより、最新の機能や技術の活用も特徴です。
オンプレミス型
オンプレミス型は、自社サーバーにチャットボットを導入するタイプです。
初期費用は高く、導入までに時間がかかりますが、セキュリティ性が高く、カスタマイズの自由度も高いのが特徴です。
特に、個人情報や機密情報を扱う金融機関や医療機関など、高度なセキュリティが求められる業界で採用されています。また、既存の社内システムとの連携がしやすいという利点もあります。
たとえば、顧客管理システムや基幹システムとのリアルタイムな連携により、より高度なサービスを提供することが可能です。
導入には専門的な知識と時間が必要ですが、長期的な運用を見据えた場合のコストパフォーマンスは良好です。

チャットボットツールおすすめ10選
ここでは、チャットボットツールのおすすめを10個ご紹介します。
ダットジャパン

ダットジャパンは、高度なAI技術を活用した対話型チャットボットを提供しています。
FAQサイトやデータベース上の情報をもとに回答でき、コールセンターやチャット業務の効率化を図れます。
自然言語処理技術により、顧客の意図を正確に理解し、適切な回答を提供できます。
さらに、コールセンター用 管理システム(CRM)やIVR(自動音声応答)/ビジュアルIVRシステムなどのシステムも提供しています。
コールセンターに関するさまざまなシステムの独自カスタマイズも可能です。自社に合わせたシステムの導入ができます。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
要問い合わせ |
|
URL |
https://datt-contactcenter.jp/ |
ChatPlus
ChatPlusは、月額1,500円から利用できるチャットボット・チャットサポートシステムです。
シナリオの作成が直感的なインターフェースで行えるため、専門知識がなくても運用が可能です。
機能数が約5,000個用意されており、その中から自社に必要な機能を選べます。LINEやSlack、Teamsなどを含めた多様な外部システムと連携も可能です。
|
初期費用 |
0円 |
|
月額費用 |
1,500円~(税抜) |
|
URL |
https://chatplus.jp/ |
Zendesk
Zendeskは、総合的なカスタマーサポートプラットフォームの一部としてチャットボット機能を提供しています。
メール、チャット、SNSなど、複数のチャネルを一元管理できる点が特徴で、既存のサポートシステムとの連携も容易です。
AIによる自動応答機能と人による対応を効果的に組み合わせえられ、複雑な問い合わせにも柔軟に対応可能です。
また、多言語対応や詳細な分析機能も備えており、グローバル展開を考える企業にも適しています。
|
初期費用 |
0円 |
|
月額費用 |
19ドル~/1人あたり(ベーシックプラン) |
|
URL |
https://www.zendesk.co.jp/ |
sinclo
sincloは、わかりやすさを重視したチャットボット型のWeb接客ツールです。
リード獲得から育成までをトータルにサポートします。ユーザーの行動履歴や属性に基づいた細かなターゲティング設定が可能で、効果的なコンバージョン率の向上が期待できます。
よくある質問や資料請求などをチャットボットに任せることで、「完全自動化」を実現できるでしょう。
さらに、チャットボットとオペレーター対応どちらも利用できるハイブリッドタイプのため、自社にニーズに合わせて選べます。
|
初期費用 |
0円 |
|
月額費用 |
10,000円~(コスト重視プラン) |
|
URL |
https://chat.sinclo.jp/ |
GENIEE CHAT
GENIEE CHATは、マーケティングとカスタマーサポート強化におすすめのチャット型Web接客プラットフォームです。
「FAQボット」「有人チャット」「チャットEFO」など、接客に必要なチャットが揃います。
オペレーター対応に切り替えも可能で、ユーザーのサポート強化につながるでしょう。
また、チャット内にユーザーの属性に応じておすすめ商品やサービスなども表示可能です。ページ遷移が不要なため、LTVアップも期待できます。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
成果報酬型(月間CV数により単価が変動) |
|
URL |
https://chamo-chat.com/ |
COTOHA Chat & FAQ
NTTグループが提供する高性能なAIチャットボットで、特に日本語での自然な対話に強みがあります。
企業の問い合わせ対応に特化しており、FAQ管理からチャットボット運用まで一元的に管理できます。
ドキュメントを読解し回答する「ドキュメント回答」は、13言語ものリアルタイム翻訳が可能です。
また、チャットボットからオペレーターへとつなぐ「オペレーターチャット」にも対応しています。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
要問い合わせ |
|
URL |
https://www.ntt.com/business/services/application/ai/cotoha-cf.html |
Bebot
Bebotは、インバウンド観光客向けの多言語対応チャットボットです。
自治体、公共機関、観光施設、宿泊施設、飲食店での導入実績が豊富で、施設案内や周辺情報の提供、予約受付など、観光客のさまざまなニーズに対応します。
AIによる自然言語処理と、位置情報を活用したレコメンド機能を組み合わせ、よりパーソナライズされた情報提供が可能です。
また、FAQ作成も任せることができ、思い通りのチャットボット実装ができます。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
要問い合わせ |
|
URL |
https://www.be-spoke.io/ |
OfficeBot
OfficeBotは、業務効率化に特化したチャットボットで、社内システムとの連携が容易です。
企業の固有データや組織内ドキュメントなど、オフィス内の情報を安心・安全に活用できます。
社内問い合わせ対応や各種申請手続きの自動化など、社内業務の効率化に効果を発揮するでしょう。
独自のプロンプト調整により、プロセスの最適化と文脈を考慮した対話機能が備わっています。
ユーザーの質問リテラシーに関係なく回答でき、回答到達率の向上が期待できます。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
要問い合わせ |
|
URL |
https://officebot.jp/ |
PEP
PEPは、シンプルな操作性と手頃な価格が特徴のチャットボットです。
特に中小企業向けに最適化された機能を提供しており、導入のハードルが低いのが特徴です。
数千万の会話データと独自の自然言語処理機能と各企業の業務に対応した辞書を標準で実装しています。
また、他のクラウドサービスとの連携も可能で、チャットボットからすぐに呼び出しできます。
|
初期費用 |
要問い合わせ |
|
月額費用 |
要問い合わせ |
|
URL |
https://pep.work/ |
HubSpot CRM
HubSpot CRMは、統合的なマーケティングツールの一部としてチャットボット機能を提供しています。
無料で導入可能な「HubSpot CRM」の1つの機能として、チャットボット作成ツールが利用可能です。
CRMに顧客情報や顧客とのやりとりを蓄積し、その都度ひきだせます。パーソナライズな対応も可能なのが魅力です。
さらに高度な機能を利用したい場合は、有料プランも用意されています。
|
初期費用 |
無料 |
|
月額費用 |
無料 |
|
URL |
https://www.hubspot.jp/products/crm |
自社に合ったチャットボットを選ぶ際のポイント
チャットボットの選定は、単なる機能比較だけでなく、自社の業務プロセスや組織体制、将来的な展開なども考慮して総合的に判断する必要があります。
以下では、主要な検討ポイントについて解説します。
導入する目的
チャットボット導入の目的は企業によってさまざまです。
たとえば、カスタマーサポートの効率化を目指す企業では、FAQ対応の自動化や24時間対応の実現が主な目的となります。
一方、マーケティング強化を目指す企業では、リード獲得や顧客とのエンゲージメント向上が重要な目的となるでしょう。
また、社内業務の効率化を目的とする場合は、各種申請手続きの自動化や社内FAQ対応などが主な用途となります。
目的によって必要な機能や適切なツールが異なるため、まずは導入目的の明確化が重要です。
社内業務の効率化を目的としたチャットボット導入をお考えの企業様は「社内向けチャットボットおすすめ7選!活用事例や選び方のポイントも紹介」記事にて詳細に解説していますので、合わせてご閲覧下さい。
AIの有無
AIの必要性は、対応する業務の複雑さや質問の多様性によって判断します。
問い合わせの種類が多く、回答のバリエーションも豊富な場合は、AI搭載型のチャットボットが適しているでしょう。
一方、定型的な業務や限られた種類の問い合わせが中心の場合は、シンプルなシナリオ型で十分な場合もあります。
近年は業務効率化を重視する企業が増えているため、AI搭載型のチャットボットが主流となっています。
特に、自然言語処理技術の発達により、より自然な対話が可能です。
AIの種類
AIにもさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。
【機械学習型】
対話データの蓄積により徐々に精度が向上していく特徴がありますが、初期の精度を高めるためには十分な学習データが必要です。
【独自AI型】
特定の業界や業務に特化した独自の人工知能を搭載しており、専門的な対応が可能です。ただし、カスタマイズの範囲が限定される場合もあります。
【RAG型】
既存の文書やマニュアルをもとに回答を生成する能力に優れており、導入後すぐに高精度な応答が可能です。
特に、既存のナレッジベースを活用したい企業に適しているでしょう。
予算やサポートの有無
チャットボットの導入には
・初期費用
・月額費用
・運用費用 など
さまざまなコストが発生します。
初期費用は数万円から数百万円まで幅広く、月額費用も利用規模や機能によって大きく異なります。また、導入後のサポート体制も重要な検討ポイントです。
技術的なサポートだけでなく、シナリオ作成支援や運用アドバイスなど、付随するサービスの内容も確認する必要があります。複数のベンダーに相談して比較検討すれば、最適な選択が可能になるでしょう。
まとめ
チャットボットの選択は、企業のデジタル化戦略において重要な決定の一つです。
導入目的を明確にし、必要な機能や予算を考慮しながら、自社に最適なツールを選ぶことが成功への近道となります。また、導入後の運用体制や改善計画についても事前に検討すれば、より効果的な活用が可能になるでしょう。